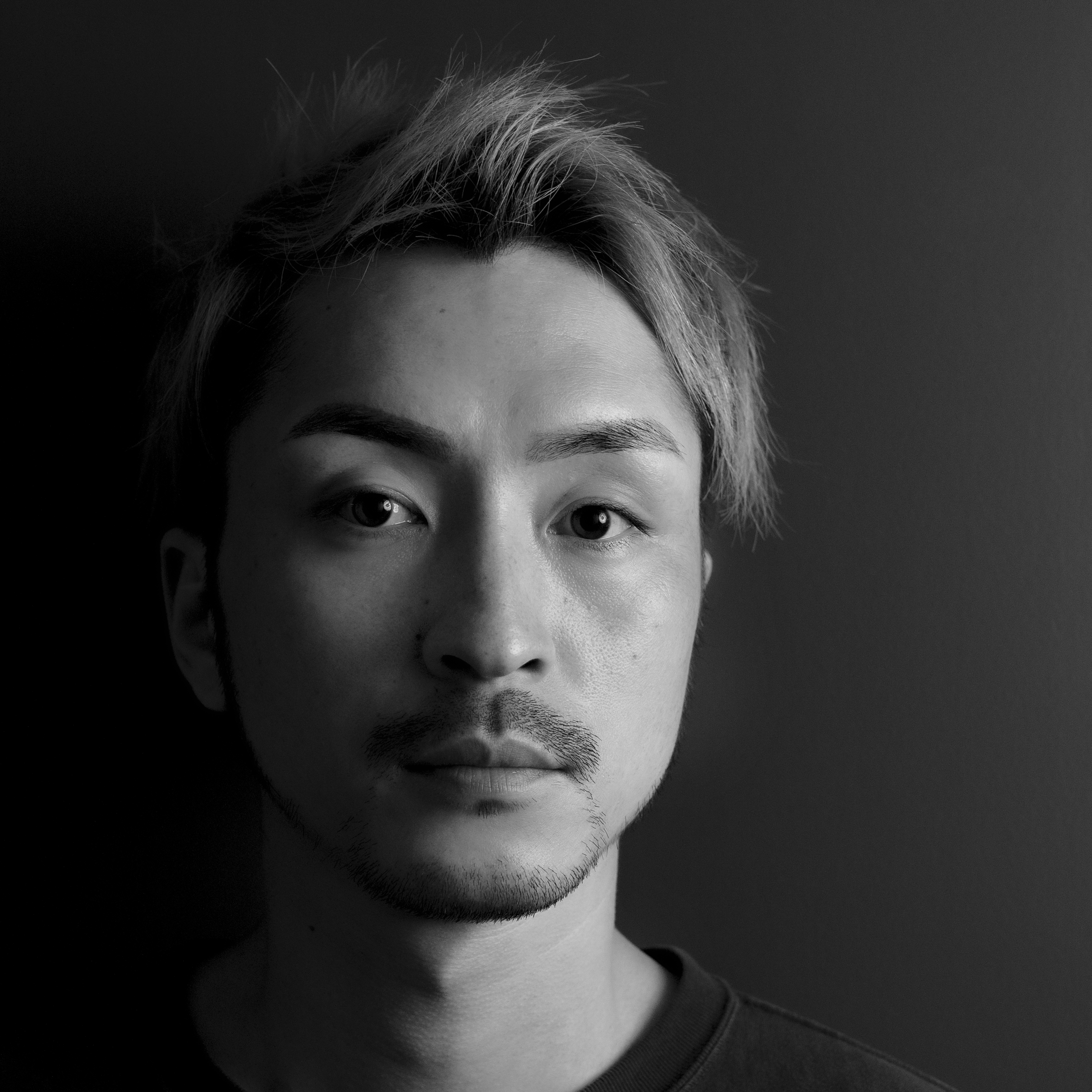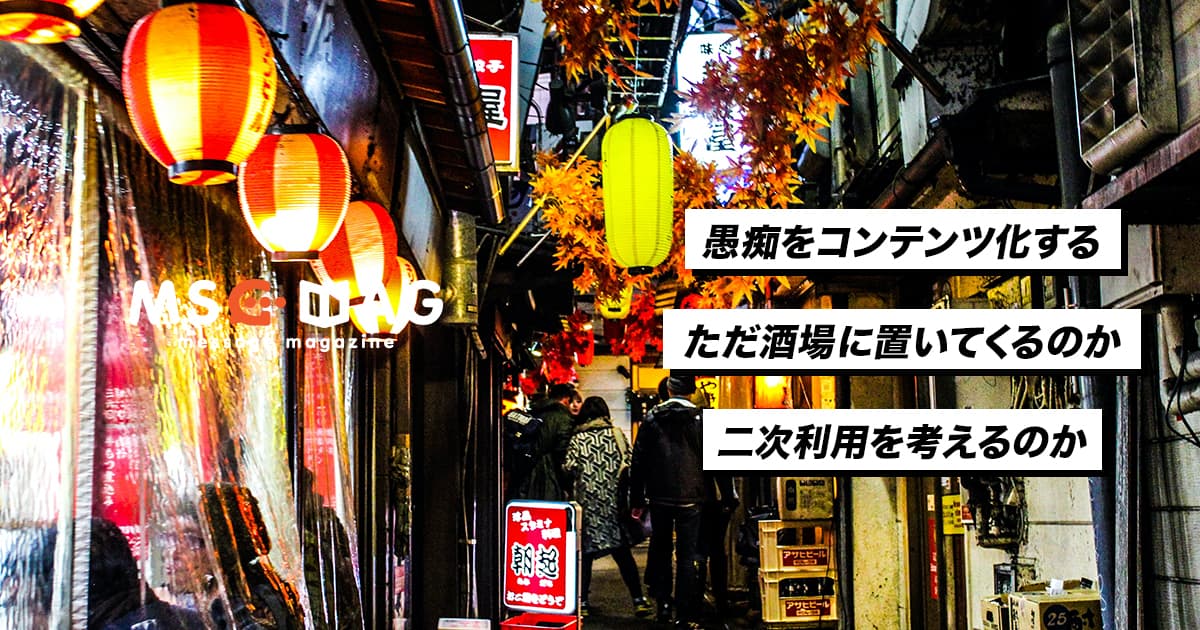
ストレス発散をクリエイティブする。
本日の記事のラジオVer.はこちらをクリック | by stand.fm
おはようございます。FOURTEENのコウタです。
京都を拠点にフリーランスデザイナーとして活動しており、毎日休まず続けている、ランニングやブログを通じて感じた「継続は力なり」の大切さを発信したりしています。
京都を拠点に完全独学のフリーランスデザイナーとして活動し6年目。2016年から禁煙をキッカケに始めた毎日ランニングは1,464日、毎日ブログは242日を突破。(2020年12月31日現在)
先日、クライアントさんとのお仕事半分、プライベート半分のようなお話しの中で「愚痴じゃないけどちょっと愚痴みたいなこと」をお話しされてたんですね。
ただ、良くある愚痴のように「誰かを傷付ける」といった感じではなく、クスッと笑ってしまうような内容で、それが次から次へと出てきて、これってすごく面白ないなと感じたんですね。
ということで今回は、ストレス発散をクリエイティブする、というお話をしたいと思います。
ブログも1つの「ストレス発散」である。
よく考えたら、僕が毎日休まず書いているブログにも「ストレス発散」という部分は少なからずあって、これまで愚痴っぽく人に話していたことを、僕はここで建設的な意見として変換して発信することが出来ています。
そういうふうに考えた時に、「愚痴を言うだけがストレス発散ではない」と思ったので、そういう感情の吐口としてブログやラジオを利用するということはすごく大切だなと感じました。
僕がこういう感覚でブログを捉えることが出来ていたからこそ、クライアントさんの「愚痴じゃないけどちょっと愚痴みたいなこと」を何かコンテンツに変換出来ないか?と考えることが出来たんですね。
半年前に見た居酒屋での出来事。
実は約半年くらい前に、クライアントさんとご一緒させていただいた飲みの席で、そこで出た「居酒屋で酔っ払った時に出た本音をコンテンツ化したら面白いんじゃないか?」と提案したところ…
一部の方から「そういう時期じゃない」と結構なストップをかけられてしまったんですね。
ですがそれから約半年が経過した今、以前と何も状況は変わっていないけど、そういう「人間味」を売っていくことが大切だというような風潮に社会がなってきました。(ただ人と同じことをする良い子ちゃんは見つけてもらえなくなった。)
僕はその時その場所にいて、居酒屋での本音に、心の底から熱いものを感じて、心の底から笑っていたんです。
これは決して「身内ネタ」ではなく、社会に対する熱いメッセージだったりを思いっきり感じたので、どうしてもこれをコンテンツ化したいと本気で思っていたんです。
ストレス発散をコンテンツ化する。
ここでただ「ストレス発散を愚痴としてコンテンツ化する」というのは本末転倒なので、ここからはクリエイターの腕の見せ所だと思っています。
おそらく「そういう時期じゃない」とストップをかけた方は、自分にコンテンツ化する能力がなかったので、仕上がりをイメージ出来なかったというのがあると思うんです。
もしその方が、僕と同じ感覚で仕上がりをイメージ出来たとしていたら、もしかしたらその場で「やりましょう!」となっていたかもしれないし、倫理やらが色々とややこしい中で、そこは否定することは出来ません。
ですが、コンテンツ制作をする上で、特にクリエイターとしては「仕上がりをイメージする力」っていうのはホントに大切なので、その出来事に対して「俯瞰で見る力」はすごく大切だったりします。
楽しむことが1番大切である。
コンテンツ制作で1番大切なのは「楽しむこと」で、やっている側が嫌々やっているものって、やっぱり相手にもうまく伝わらないんですね。
今回、クライアントさんが抱えている「普段思っているけど言えないこと」を、もしも僕がうまくコンテンツ化出来たとしたら、「ストレス発散をコンテンツ化する」という理想の形を作ることが出来るんです。
ここで「ストレス」を考えた時に、人は毎日、多かれ少なかれストレスを感じて生きているので、要するに「尽きないネタ」を手に入れることが出来るということですね。
更にそれを「みんながクスッと笑えるコンテンツに変換する」ということが出来たとしたら、これ以上Win-Winなことってないですよね。
これに関しては、もうすでに昔からお笑い芸人さんや、YouTubeのコンテンツとして山のように作られていますが、コンテンツを作るネタとして「ストレス発散」が実は代用されているよということが伝われば良いなと思います。
不平不満は皆さんあると思いますし、時には愚痴を言いたくなることもあると思いますが、それをただ酒場で置いてくるのか、もしくはコンテンツとしてどう発信するかを考えるのかで少し差が生まれると思ったので、そこを改めて考えると面白いかもしれません。
一緒に頑張りましょう。
では、また明日。